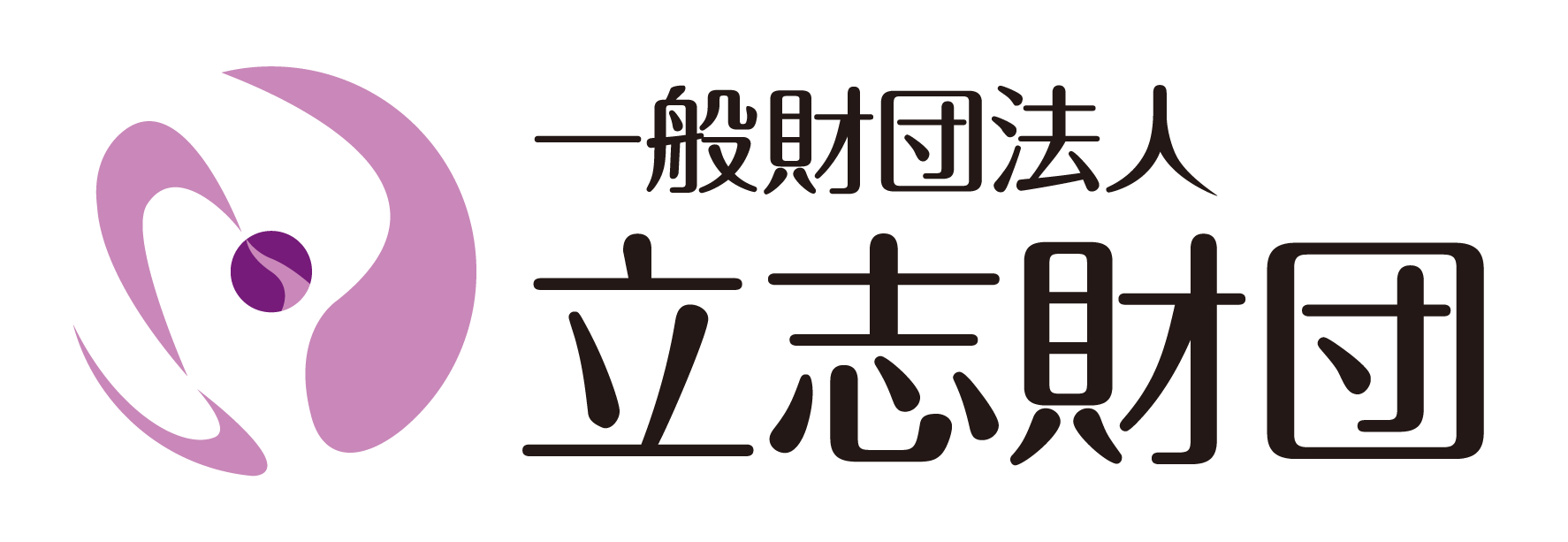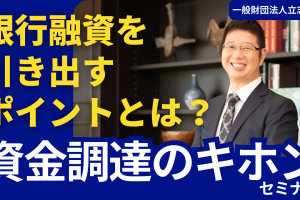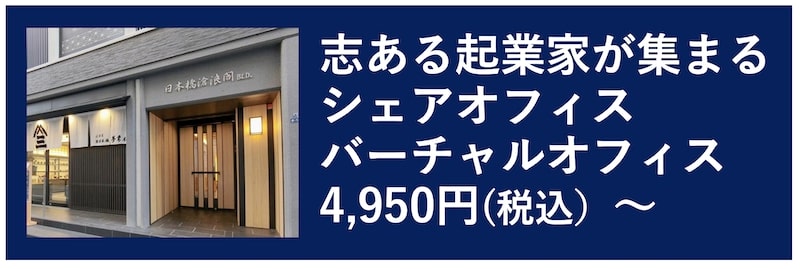今回の立志インタビューは迫田恵美さんです。迫田さんはバックオフィスのサポート業務の会社の経営と日本神話である古事記を伝える活動。また熊本県菊池市での農業という三刀流で活躍をされています。
古事記を伝える活動の中でお米が神話と切っても切れない存在であると気づき、農家の高齢化や食料自給率の低さに強い危機感を抱きました。この危機感と不思議なご縁に導かれ関東と熊本で二拠点生活をスタート。「ありのままの自分を愛せる人で満ち溢れた社会を作る」という真志命に基づき日本の心と「いのち」を耕す挑戦を続けています。そんな迫田さんに今の活動から過去の話、未来の展望などを伺いました。

迫田恵美(さこだ・えみ)
熊本県出身。地元熊本で九州一円のレンタルビデオ店の卸会社にて経理・総務・労務・販売管理業務等に携わる。バックオフィス業務と並行してセミナーのアシスタントや企画・営業なども経験。さらに経営コンサルティング会社に異動し事業再生・経営支援にも関わりながらグループ会社やクライアントなど複数の法人のバックオフィス業務の統括を行ってきた。ひとりで何役もこなす必要のある中小企業のバックオフィス業務に15年以上携わってきた経験を活かし2018年独立。現在は「古事記」を広める活動で毎月の読書会の開催や「絵本 やまとことば神話」の読み語り会、セミナー開催なども行っており、2024年からは熊本県菊池市に移住し、農業の分野での事業展開を視野に入れて活動中。
神話と食のつながりから、農業の道へ
-現在取り組まれている活動を教えてください。
大きく分けて3つの活動をやっています。1つ目はバックオフィスのサポート業務です。これは2018年に独立して個人事業でスタートし途中で法人化もしました。経理を中心とした業務や事務局業務を企業様に合わせてカスタマイズしながら請け負っています。仕事は基本的に遠隔でパソコンさえあればどこででもできる業務です。
2つ目が日本の神話である古事記をお伝えをする活動です。漢字や外来語が入る前から使われていた大和言葉(元々の日本語)と古事記を通じて日本人としての根幹の部分を伝えています。多くの日本人が日本のルーツを教わらずに育ってきた中で私自身がその価値を知り「自分は自分でいいんだ」と思える自己肯定感を持てる人を増やしたいです。それによって幸せに思う人が増えてほしいという思いで活動しています。古事記の絵本(絵本やまとことば神話)やワークショップ、イベントなどを通じて伝えています。
3つ目が農業に関する活動です。2024年の7月から熊本の菊池市というところで東京と熊本の二拠点生活をしてお米作りや地域貢献に関わっています。神話を伝える活動をする中で、「お米」や「食」が神話と切っても切れない存在だと感じました。土を耕さないと良い作物が育たないのと同じように人間の体も耕さないと良い教えが入っていかないことに気づきました。ちょうどその頃米農家さんの平均年齢が70歳を超えているという現実や後継者がいない問題といった日本の食料自給率が低いという現実を知り「このままだと10年後どうなるんだろう」と強い危機感を覚えました。この現状をどうにかしたいと思ったことがキッカケです。
偶然の出会いが古事記を伝える活動に
-古事記を伝える活動を始められたのは何かきっかけがあったのでしょうか?
古事記については独立して相談していた税理士の先生にアメリカのシャスタへのツアーに誘われたことが大きなきっかけです。元々予定があったのですが偶然空きができて行くことになりました。そのツアーの主催者が日本のことや脳科学を教えている方でその方とのご縁で言霊塾という塾に通い日本のことを色々教えてもらう中で日本神話や日本の歴史ついて知っていきました。そこから今までほとんど行かなかったのですが神社に行くようになったりと変化がありました。日本って素晴らしい国だなって気づきました。そこから縁あって「古事記」を広める活動を始めて毎月の読書会の開催や「絵本やまとことば神話」の読み語り会、セミナー開催なども行うようになりました。

やまとことば語り部協会認定の言本師(ことのもとし)として活躍中!日本全国に仲間がいます。
-そうだったんですか!そこから農業への関心は何かキッカケがあったのでしょうか?
日本神話を伝える活動をしていく中でお米が神話と切っても切れない存在だと感じるようになりました。『古事記』や『日本書記』によれば稲をはじめ五穀は神が生み成されたものと語られています。ちょうどその頃、米農家さんの平均年齢が70歳を超えているという現実や後継者不足、日本の食料自給率が低いことを知りました。
-現状への強い危機感があったのですね。
「このままだと10年後どうなるんだろう」と強い危機感を覚え、「どうにかしなきゃ」と思ったんです。体が耕されないと良い教えが入っていかないように、土を耕すことの重要性にも気づきました。
不思議なご縁に導かれて熊本県菊池市へ移住
-菊池市への移住は、その危機感が後押ししたのでしょうか。
まさにそうです。関東に住んでいた頃から農業に関わっていましたが、もっと身近でやりたいと思っていた時に20年前に数回会ったきりの菊池市の農家さんとの不思議なご縁がありました。その方と話すうちに神話と農業が深く通じていることに感動しました。もうウカウカしていられない、早くやらなきゃという「せかされるような思い」もありお会いしてから半年後という早いタイミングで移住を決めました。
-その移住の決断や活動を進める中でこれまでで一番「やってよかった」と思えた出来事は何でしょうか?
不思議なくらい縁が繋がっていることです。菊池市に来た当初はその方しか知り合いがいなかったのですが今ではお友達やこれからの日本を考える仲間たちと出会うようになりました。菊池市に住むにあたって普通のアパートはもったいないと思い、最初に入ったシェアハウスが農家で地域でも大きな会社をされている会長さんが運営されているところでした。本当に大事な人と合わせてもらえていると感じていて神様が応援してくれているんじゃないかと思えるようにました。

迫田さんも農作業をされます。インタビューした日も畑に行った後にお話しをお伺いしました。
大切なことはご縁が来た時にチャンスに飛び込むこと
-本当に素敵なご縁でつながったんですね。そんな中でこれまでの活動で大切にされていることは何でしょうか?
私は「これが絶対やりたい」という強烈なタイプではなく流されるままに生きてきた人でした。ですがご縁や誘いのメッセージが来た時にチャンスに飛び込み行動することは大切だと思います。1年前の自分が想像もしていなかったことができます。まずは断らずにチャンスに飛び込むことは大切にしております。
その結果、菊池の地で今年からお米を扱わせていただけるようになりました。菊池市は2000年以上続く米どころで、江戸時代にはその年のお米の価格を決める基準になっていたお米が作られていた場所です。この地域の魅力を発信と流通を作っていくことに貢献できるのは大きな一歩です。私たちはこの地域のポテンシャルを活かしブランド力で有名な南魚沼産に負けないくらい「菊池産」といえば食べたいと言われるように貢献したいです。
ありのままの自分を愛せることが幸せの根幹
-素晴らしい挑戦ですね。そんな迫田さんの人生の目的や真志命はなんでしょうか?
私の真志命は「ありのままの自分を愛せる人で満ち溢れた社会をつくる」ことです。漠然と「みんなが幸せだったらいいな」と思っていましたが幸せとは何かと考えたときにありのままの自分を愛せることや自分が自分でいいと思えることが幸せの根幹だと気づきました。そういう人が増えればこの世の中は幸せで平和になると思っています。
-その使命を明確に言葉にできるようになったキッカケは立志財団の「真志命コース」に参加したことが大きかったのですね。
そうですね。参加させていただく前は漠然とした思いでしたが真志命コースを受ける中で、私の中のひとつの答えとしてそれはありのままの自分を受け入れ、認められることなんだと思いその思いを言葉にすることができたので自分に確信を持てるようになりました。やっぱり自分が自分でいいっていう思えることが幸せの 1 つなんじゃないかなと思ってます。ありのままの自分を愛せるっていう人が増えていけばこの世の中って幸せで平和なんじゃないかなと思ってます。
事業計画だけでなく祖先や宇宙と自分がつながっているところが立志財団の良さ
-素敵な考え方ですね。ちなみに迫田さんにとって立志財団はどのような点が魅力的でしたか。またどのような方にお勧めしたいと思いますか?
多くのコンサルや団体がある中で立志財団を選んだのは現実的な事業計画だけでなくご先祖様や宇宙と繋がっているというところを大事にされ伝えられているところは少ないのではないかと思うのでその点は強く共感していいなと思いました。
農家が正当に報われる仕組みをつくりたい
-今後の農業・地域活動を通じて、どのような社会を目指していきたいですか?
最終的な目標は「農家さんがきちんと稼げる流通を作ること」です。今の社会で最も大切な役割を担っている農家さんが、適正な価格で報われて若い人たち希望を持てるようにしたいです。また菊池市では若い移住者が多く、農業に関心のある方も多いです。彼らや地元の農家さんや地域を盛り上げたい方たちと一緒にこれからの日本のあり方や新しい価値観を創造していけるような菊池市をモデルケースとする活動を始めています。菊池市は「癒しの里」とも言われているので福岡など都市部から癒しに来られるような場所づくりも模索しています。
-ワクワクしますね。
また農業が持つ社会的な役割を伝えたいです。例えば、熊本にはきれいな水があるため半導体工場をはじめ様々な産業の工場もが進出していますが、その水は山に降った水が田んぼに貯水されて地下水となって流れてきたものです。農業は食べ物を作るだけでなく環境維持や防災にも役立ちます。将来的には福利厚生やCSR活動の一環として、企業の方々に現地で農作業に関わっていただき、収穫されたお米を社員さんが食べる形で繋がりを感じられる仕組みを作っていけたら嬉しいです。
-単にお米だけではなく半導体を作るなどの様々なことにつながっているんですね。
そうですね。将来的には企業研修や企業のCSR活動の一環として企業の方々に現地で農作業に関わってもらいそのお米を社員さんが食べるという形で繋がりを感じられる仕組みを作っていけたら嬉しいです。
“いのち”を耕し、“心”を育てる
-今後、農業や古事記の活動を通じて、どんな未来を描いていきたいですか?
農家さんが食を一番支えている人たちなのに一番大変な思いをしています。彼らが経済的に報われ農業を「自分事」として関われる人を増やしたいです。古事記の活動を通じては自分が自分でいいんだとありのままの自分を愛せると思える。自己肯定感を持てる人を増やしたいです。
-最後に読者の方へひとことお願いします。
皆さんお米を食べてください! ぜひ私の家から5分程度の近くの田んぼで作っているお米を試していただけると嬉しいです!
-ありがとうございました。

2000年以上の米作りの歴史がある熊本・菊池の田んぼ
【まとめ】お米は日本人の命。ぜひ菊池米を食べてみたい!
今回の迫田さんのお話しをお伺いして迫田さん自身は特に「これがやりたい!」という強い意志があってここまで来たのではなく、偶然の出会いで今の活動に至ると話されていました。しかしその一つ一つの出会いを大切にされたことが神様のプレゼントで熊本・菊池に導かれたのではないでしょうか。2000年以上の米づくりの歴史があり、お殿様にも献上されていた菊池米。ここまで読んでいただいたあなたもぜひ一口味わってみませんか?
迫田恵美さんが販売しているお米「こめこめマルシェ」はこちらから
迫田恵美さんのフェイスブックアカウントはこちらから
また迫田恵美さんがおすすめした立志財団の「坂本立志塾 真志命コース」はこちらから
取材・執筆=木村元康